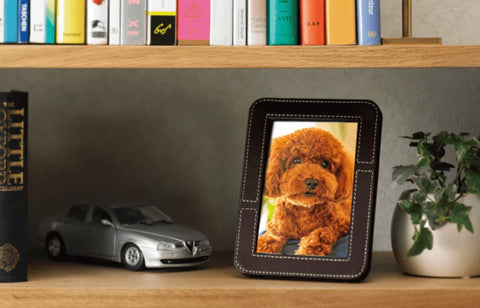当店では、毎日、愛するペットを喪われた方と接しさせていただいております。
その中でよく相談を受けるのは「ペットロスを乗り越えるためにはどうすればよいでしょうか?」ということです。
愛するペットを喪ったわけですから、簡単に克服できるものではありません。
私はいつも次のようにアドバイスさせていただいていいます。
ペットロス大変お辛いと思います。
私がアドバイスさせていただけるとするならば、ペットロスを乗り越えるためには、自分の悲しい、辛い、苦しい、寂しい、あのときこうしていればと言った後悔、すべての気持ちを受け止め、心のまま吐き出してください。
ひたすらただ話を聞いてくれる家族、友人がいれば良いですが、いなければ悲観することなく、泣いて泣いて涙枯れるまで泣きまくって良いと思います。
いつまでも引きずる自分はおかしいと思う必要は全くありません。
人として当たり前の感情ですので安心してください。
ペットロスにはおよそ4段階の心理過程があります。
少しかたい言い方になりますが、
- 死のショックを受けている【衝撃期】
- 喪失の原因を探す【悲痛期】
- 死を受け入れ、我が子に出会えた事を感謝できるようになる【回復期】
- 次の子を考えることができるようになる【再生期】
大まかにはこのようにいわれています。
この心理過程を行ったり来たりすることもありますが、徐々に回復期、再生期を迎える事ができます。
焦らず、自分の心理過程がどこなのかを知ることで、どこまで自分が進んでいるのかの目安になるかと思います。
何度も申し上げますが、ひきずる気持ちはおかしなものではありません。
悲しみを受ける衝撃の大きさも人それぞれです。
比べるものではありません。
自分の悲しみの大きさは自分だけがわかってあげられるものです。
自分に素直に、悲しければ自分もういいと思えるまで泣く。気持ちを吐き出す。
それがペットロスを乗り越える一番の早道かと思います。
少しでも参考になれば幸いです