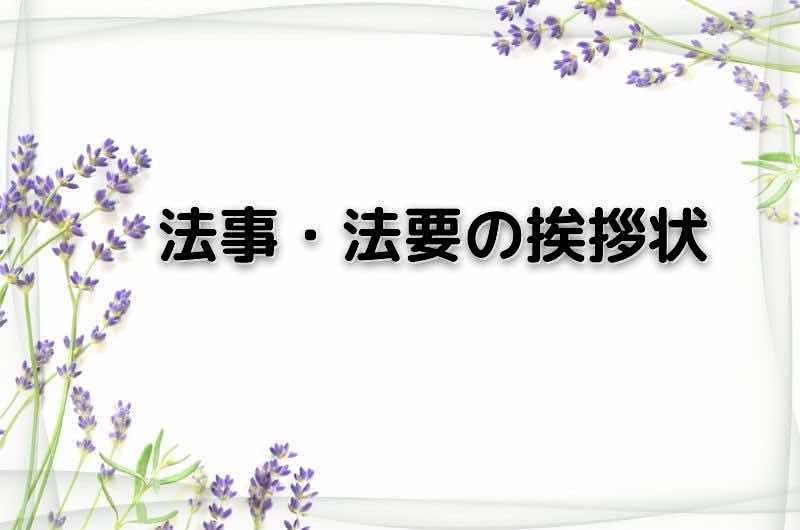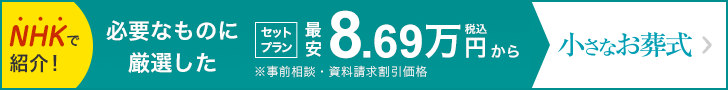四十九日法要が終わった後は、一周忌・三回忌などの「年忌法要」が行われます。
そこで出す必要があるのが「法事の案内状」です。
この記事で、法事の案内状を出すときに注意するポイント・例文を確認していきましょう。
法事の案内状の基本
忌明けの法要後は、命日に「年忌法要」を営みます。
命日が平日などで都合がつかない場合は、命日より前の日に繰り上げて行われます。
年忌法要の案内の出し方
法要を行うときは、事前に案内状を出して出欠席の返事をもらうようにします。
ある程度余裕を持たせるために遅くとも二週間前には届くように送りましょう。
案内状は封書で二重封筒は避けます。
返事が欲しい場合は返信用はがきを同封します。
最近では略式で往復はがきが使われることも増えてきています。
案内状の内容
案内状では時効の挨拶や相手の健勝を伺う挨拶など、前文を省略しません。
主文では、法事の案内の必要事項を簡潔に記します。
- 「誰」の「何回忌」か
- 日時・場所
- お斎(会食)の有無
- 返事の期日
案内状を出すのは三回忌くらいまで
法事は年を進むごとに小規模にしていきます。親族以外の友人・知人を招待するのは、三回忌くらいを目安に、それ以後は近親者のみになるので案内状を出す必要もありません。
法事の案内状の例文

※縦書を想定しています。
(①前文)
さて 来る◯月◯日は亡父◯◯の一周忌にあたりますので 左記のとおり心ばかりの法要を営みたく存じます
ご多用中誠に恐縮でございますが ご参会賜りますようお願い申し上げます
(②法要の案内と出席のお願い)
なお 当日は法要ののち 粗餐を差し上げたく存じます 謹白
(③お斎の有無)
まずはご案内申し上げます
平成◯年◯月◯日
施主 ◯◯◯◯
記
一、日時 ◯月◯日(◯)午前◯時より
一、場所 ◯◯県◯◯市◯◯区◯-◯-◯ ◯◯寺本堂
まとめ
いかがでしたか?
法事・法要の文例をみてきました。
他にも挨拶状の文例はこちらの関連記事にあります。
【関連記事】
>忌明け・香典返しの挨拶状
合わせてご確認くださいね。