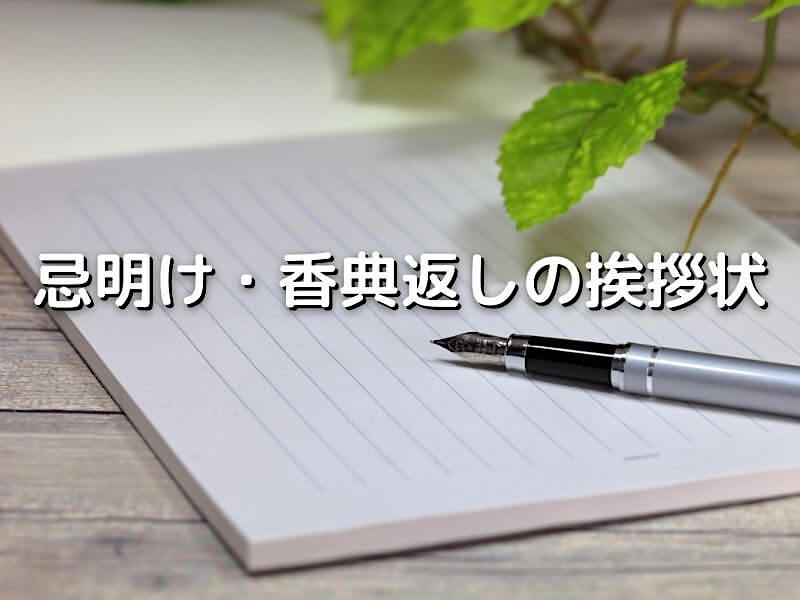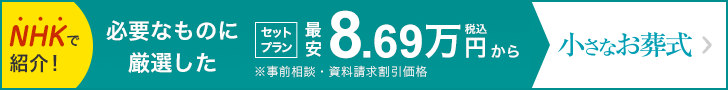この記事では、「忌明け・香典返しの挨拶状の基本」も踏まえながら、挨拶状の例文をみてきます。
(この記事の下に移動します。)
さて、四十九日法要が終わると「香典返し」を行いますが、これに忌明けの挨拶状を添えて出していきます。
挨拶の内容は、忌明けの報告や香典へのお礼です。
そして最近では葬儀当日に返したり、香典を寄付したりと、色々と変化が見られます。
では、忌明け・香典返しの挨拶状の基本を、例文を交えて見て行きましょう。
目次
忌明け・香典返しの挨拶状の基本
忌明けの挨拶状は返礼の品に添えるのが一般的です
一般に仏教では四十九日をもって「忌明け」になります。
その忌明けに、通夜や葬儀で香典をもらった人に対してお礼の品を贈るのが香典返しです。
この返礼品に挨拶状を添えて出すのが忌明けの挨拶状の基本となります。
なお「忌明けの挨拶状」は印刷して出すことが多く、ほぼフォーマットが決まっています。
特に親しい人に対して形式的すぎると思った時は、一筆加えるのも良いですね。
香典返しを葬儀当日に渡している場合
最近では葬儀当日に香典返しをする「即日返し」(当日返し) という方法が増えています。
この場合、忌明けの挨拶状は改めて出す必要はありません。
ですが、忌明けの挨拶状だけでも贈ると丁寧です。
また、即日返しで想定していたよりも多い金額の香典をもらった人に対しては、不足分を改めて贈ることが一般的です。
その際に忌明けの挨拶状を添えるようにしていきます。
香典返しをしない場合
香典を養育費・生活費にあてる場合
香典は香を手向ける代わりであり、遺族を経済的に支援するのが目的です。
故人が一家の働き手で子供がまだ小さい場合などは、養育費や生活費にあてても良いとされています。
この場合は香典返しをする必要はなく、忌明けの挨拶状でその旨をお知らせします。
香典を寄付する場合
最近増えているのが、故人の意志や遺族の希望で、香典を「福祉施設」や「医療機関」に寄付するケースです。
この場合も、寄付する旨と寄付先を挨拶状に明記します。
【関連記事】
香典の寄付を受け付けている団体まとめ
忌明け・香典返しの挨拶状の例文
それでは、基本の例文から順に見ていきましょう。
基本の例文
(①会葬・香典への御礼)
おかげをもちまして本日
◯◯院◯◯◯◯居士
七七日法要を滞りなく相営みました 感謝をもってご報告申し上げます
(②忌明けの報告)
つきましては供養のしるしまでに心ばかりの品をお届けいたしました 何とぞご受納くださいますようお願い申し上げます
(③返礼品の送付)
さっそく参上いたしまして御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちまして 謹んでご挨拶申し上げます 謹白
(④略儀の挨拶の詫び)
平成◯年◯月◯日
香典を養育費に当てる場合
先般、夫◯◯の死去に際しましては、お心のこもったご弔慰をいただき、そのうえ過分のご芳志まで頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。
おかげさまで、本日、故人の七七日忌にあたり、無事法要をすませることができました。ここに謹んでご報告申し上げます。
本来ならば、ご弔慰への謝意を表し、御礼をさせていただくべきところではございますが、甚だ勝手ながら日頃のご厚情に甘え、遺児の養育費にあてさせていただきたく存じます。
どうかご寛容をもってご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
略儀ながら、書中をもってご挨拶申し上げます。 かしこ
香典を寄付する場合
このたび父◯◯永眠の節は、お心のこもったご弔詞をいただき、かつまた格別のご芳志を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。
おかげさまで故人の満中陰の法要を滞りなくすませることができました。感謝とともにご報告申し上げます。
つきましては、誠に勝手ではございますが、ご芳志の一部を故人の意志により日本◯◯協会へ贈り、ご返礼に代えさせていただきました。何とぞご了承いただきたく、お願い申し上げます。
まずは略儀ながら、書中にて謹んで御礼かたがたご挨拶を申し上げます。 敬具
まとめ
いかがでしたか?
ここまで、忌明けの挨拶状の基本と例文を見てきました。
ご参考になりましたら幸いに存じます。
なお、会葬礼状についてはこちらにまとめてあります。
合わせてお読みくださいね。