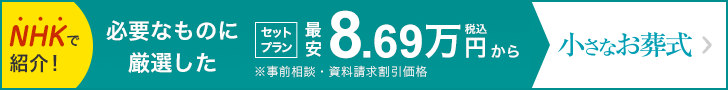【葬儀の手順】
- 危篤から安置まで (危篤、臨終、連絡、安置、役所への手続き)
- 安置から納棺まで (葬儀日程の決定、斎場の決定、戒名と御布施の用意、納棺)
- 通夜 (通夜の準備、通夜の流れ、通夜振る舞い)
- 葬儀・告別式 (葬儀告別式の準備、流れ、お布施の包み方・渡し方)
- 出棺・火葬から精進落としまで ( 出棺、火葬場への移動、繰り上げ初七日法要、精進落とし、葬儀後の手続きの整理)
遺体を自宅に安置したら、お通夜と葬儀の準備をしなければなりません。葬儀の日程、内容を決める大事な段階である安置から納棺までの流れを見ていきます。
目次
葬儀の日程を決める

喪主と葬儀の方針を決める
まず、「喪主」を決めていきましょう。
喪主は、配偶者、長男、次男…、長女、次女…という順で決めていきます。
子が親より先に亡くなった場合は「逆縁」といい、本来なら親は喪主をやらないのですが、現在では親が喪主をやるのも一般化してきているようです。
そして、必要なら「世話役」も決めていきましょう。
ただ最近は小規模化しているので「世話役」を頼まないことも。
世話役は葬儀規模に応じて、役割分担をします。
喪主や世話役が決まったら、次は「葬儀形式」「葬儀の規模」、「予算」や「式場」を決めていきます。
菩提寺の都合を聞いて日程を決める
菩提寺とは分かりやすく言えば、家と寺との間の契約関係のことです。
菩提寺がなければ、遺族が日程を決められます。
一方、菩提寺がある場合は、菩提寺の都合を聞いて日程を決める必要がでてきます。
また、日程調整については火葬場を押さえなければなりません。火葬場は「友引」の日は休んでいることが多いので注意が必要です。
菩提寺が遠方にあり、葬儀が困難な場合は菩提寺に近くのお寺を紹介してもらえないか聞いてみましょう。
また、菩提寺に無断で葬儀を執り行うと納骨を断られることも・・・
注意が必要です。
斎場を決める
通夜・葬儀・告別式を行う施設
斎場とは「通夜・葬儀・告別式」を行う施設のこと。
昔は自宅で執り行うことが多かったのですが、現在では斎場の利用するのが一般的です。
公営斎場と民営斎場
まず、「公営斎場」は地方自治体などが主体となって運営している斎場です。
使用料が安く、火葬場を併設していることが多いという特徴があります。
ただし「時間制限」や「利用者の住所制限」があったり、交通の便があまりよくない場所にあることも。
また人気が高く、希望の日程で予約をとれることが難しくなっています。
一方、「民営斎場」は多少割高にはなるものの、アクセスが良好な場所にあることも多く、式のプログラムや出棺時間などの面で融通が利きます。
戒名とお布施の用意

菩提寺に納骨するためには基本的に戒名が必要
戒名は本来、仏弟子に与えられる名前のこと。
現代では葬儀の際に、導師に戒名を授けてもらうことが一般的です。
したがって「菩提寺」がある場合、菩提寺の住職から戒名を授けてもらわなければ、原則としてそのお寺には納骨できません。
無宗教の霊園などに納骨する場合は戒名が不要ですが、寺院に納骨する際は戒名が必要かどうか確認しておきましょう。
戒名のランク
現在の傾向として、戒名料によって戒名のランクが変わる風潮があります。
金額により「信士・信女」「居士・大姉」などの位号が変わったりします。
また高額な戒名料を払えば「院居士・院大姉」などの院号のついた戒名を授かることも出来ます。
お布施の金額
戒名料は葬儀へのお礼とあわせて「お布施」として渡すことになります。
お布施は「気持ち」です。
値段は決まっておらず、分からない場合は直接菩提寺や檀家総代に問い合わせると良いでしょう。
また、葬儀社からの紹介の場合、お布施の金額が提示されることが多くなっています。
納棺
死に装束を着せ、遺体を棺に納める
本来は遺体を入浴させ清める「湯灌」を行います。
それが現在では「清拭」で簡易に済ませることが多くなっています。
また昔は、遺族のみで行うものでした。
現在では葬儀社主導のもとで「納棺の儀」を執り行うことがほとんどです。
そこ後、あの世への旅の支度として、足袋、脚絆、手甲を着せていきます。
副葬品を入れる
納棺の儀の際、故人の愛用品などを「副葬品」として一緒に収めることもできます。
この際、
- 燃えないもの
- 燃えると有害物質が出るもの
- 溶けて遺骨や炉を傷つけるもの
葬儀の規模や内容についてしっかり葬儀社と相談するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
ここまで葬儀の流れをみてきました。
次はこちらです
葬儀の流れを知る(3/5) 通夜
この記事がお役に立てましたら幸いです。
【葬儀の手順】
- 危篤から安置まで (危篤、臨終、連絡、安置、役所への手続き)
- 安置から納棺まで (葬儀日程の決定、斎場の決定、戒名と御布施の用意、納棺)
- 通夜 (通夜の準備、通夜の流れ、通夜振る舞い)
- 葬儀・告別式 (葬儀告別式の準備、流れ、お布施の包み方・渡し方)
- 出棺・火葬から精進落としまで ( 出棺、火葬場への移動、繰り上げ初七日法要、精進落とし、葬儀後の手続きの整理)