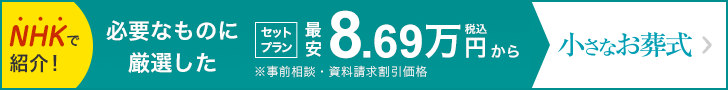ご存じかと思います。
喪中には、お祝い事をしないものです。
しかし、お正月は新年をお祝いして初詣に行ったり、おせち料理やお雑煮、お屠蘇などの祝い膳を家族で食べたり、しめ飾りを飾ったりします。
では、これらは喪中にしてはいけないのでしょうか?
この記事では、喪中の正月過ごし方について解説していきます!
目次
喪中に初詣に行くのはOK?
喪中に初詣は控えた方が良いと思われがちです。
ですが正確には違います。
神社への参拝を控えるのは「忌中」です。
では「喪中」と「忌中」の違いはなんでしょうか?
「喪中」も「忌中」も自宅にこもって身を慎むことを意味します。
しかし、期間が異なります。
「忌中」は不幸があってから、仏教では49日、神道では50日とされます。
それが、一般的です。
一方で「喪中」は宗教を問わず一般的に一年間とされています。
つまり、神道では忌中があけた51日以後であれば、穢れが晴れているという考えなのです。
参拝は問題ありません。
そして、仏教には本来「穢れ」の概念はありません。
忌中に迎えた正月に初詣をしたい場合はお寺にお参りするのも良いかもしれません。
また、神社もお清めの儀式などを行うことで参拝が許可されることもあります。
それでも、どうしても神社に参拝したい場合は相談してみましょう。
喪中におせち料理を食べるのはOK?
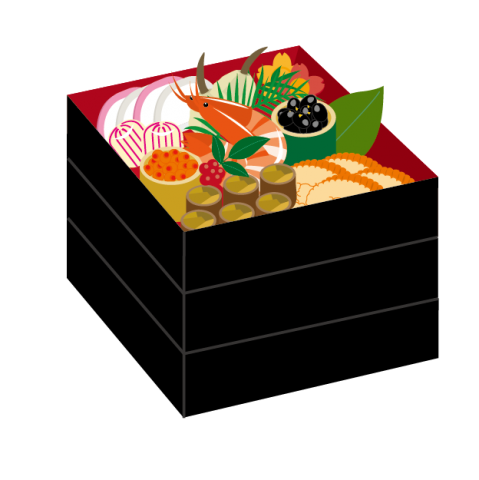
おせち料理の由来とは
お正月といえば、豪華なおせち料理ですよね。
おせち料理の由来は、作物の収穫などを感謝して神様にお供えした「節供」を料理して食べた「節供料理」とされています。
奈良時代には朝廷内の節会で料理が振舞われるようになりました。
次第に一般市民にも浸透し、最終的には五節供のうち最も重要な正月の節供料理をおせちと呼ぶようになったと考えられるそうです。
おせち料理の意味
おせち料理は「祝い肴三種」と「煮しめ」「酢の物」「焼き物」を基本とします。ただし地域によって内容も異なります。
黒豆は黒く日焼けするほどマメに働けるようにという無病息災を願ったものです。
数の子は卵の多さとニシンが二親に通じて子孫繁栄、田作りは五穀豊饒など、それぞれの料理に縁起が良い意味が込められています。
重箱に詰める意味とは
おせちは「組重」を用います。これはめでたさを重ねるという意味が込められています。
おせちの重箱の段数は五段重が正式であったと言われています。
現在では四段重が一般的です。
「一の重」には三つ肴と口取り、「二の重」には焼き物、「三の重」と「与の重」には煮物or酢の物どちらかを入れます。
四段目が「与の重(よのじゅう)」と呼ばれているのは、「四」という数字が死を連想させるためです。
おせち以外のお正月の祝い膳
お雑煮
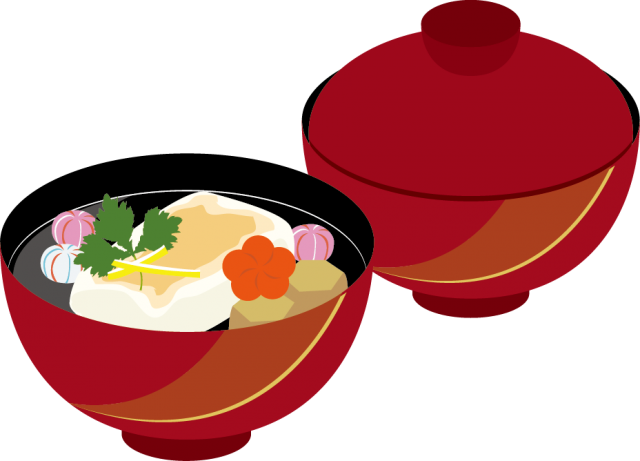
おせち料理に並ぶお正月の代表的な料理といえば、お雑煮ですよね。
地方によってお餅の形や具の種類などが異なりますが、沖縄を除く日本全国でお雑煮を食べる風習があります。
正月飾りの鏡餅に代表されるようにお餅は歳神様へのお供えです。
旧年の収穫や無事に感謝し、新年の豊作と家内安全を祈るためにお雑煮で食べるようになったと言われています。
お屠蘇

お正月にはお屠蘇という、縁起物のお酒を飲む風習があります。
お屠蘇という名前には「邪気を屠り魂を蘇らせる」「蘇という悪鬼を屠る」など様々な解釈があります。
お屠蘇は数種類の生薬を酒やみりんで漬け込んだ薬草酒で、正式には屠蘇延命散と言います。
その名の通り、邪気を払い長寿を祈るお酒で、新年を祝うおめでたい席で飲むお祝いのお酒です。
お屠蘇の器は屠蘇器を用いるのが正式です。
元旦の朝に汲んだ水(若水)で身を清め、神棚や仏壇を拝んだあとに、お雑煮やおせち料理などの祝い膳を食べる前にお屠蘇を飲みます。
お屠蘇を飲むときは一家そろって東の方角を向きます。お屠蘇は一般の酒席とは逆に年少者から順に盃を進めます。
これは長寿を願い、若さを年長者へ渡すという意味が込められています。
祝い箸
売り上げランキング: 178,782
祝い箸は箸の両側の先端が細くなっているお箸です。
両方の先端が細くなっているのは、片側が神様用で、片側が人間用という、神様にお供えしたものを下げて食べるための作りです。
そのため、逆側で食べたり取り箸として使うのはNGです。
お正月のおせち料理やお雑煮など、祝い膳を食べるときなどに祝い箸は欠かせません。
喪中のおせち料理、祝い膳は基本的には控えたほうがよい
喪中はお祝い事を控える期間です。
その点、おせち料理は新年をお祝いする料理ですので、基本的には喪中におせち料理は控えたほうがよいとされています。
おせちと同じく、お雑煮やお屠蘇も祝い膳ですので、同様に喪中には控えたほうがよいとされています。
喪中のお正月はお祝いの食事をせずに、日常的な食事で迎えるということになります。
正月におせち料理がないのは寂しいという人は
それでも、おせちやお雑煮のないお正月はどこか寂しいものですよね。
喪中のおせち料理はお雑煮などは様々な考えがあり、実際に食べている人もいます。
例えば、
- 重箱や祝い箸は使わない
- お祝いの食事としてではなく、日常の食事として食べる
- 紅白のものを白にしたり、鯛などの華美なものを避ける
- 喪中でも忌明け後であれば食べてもよい
いずれにせよ、おせち料理は家庭内のことです。
家族の意向を尊重することが大事です。
おせち料理はあくまで日常の食事としていただき、新年のお祝いを自粛して故人を偲ぶのであれば差し支えもないのではないと言えそうです。
喪中のお節料理のまとめ
- お正月のおせち料理、お雑煮、お屠蘇などの祝い膳は基本的には喪中は控えなければならない
- ただし、家庭内のことなので、お祝いではなく普段の食事としてそれらを食べる家庭もある
喪中に正月飾りを行うのはOK?
正月飾りは縁起の良いものを飾って歳神様を迎える風習
日本の年始は自宅に様々な縁起の良いものを飾ってお正月を迎える風習があります。
この飾りを正月飾りと言います。
正月飾りと言って思い浮かぶのが、家の門や玄関前に飾る門松(松飾り)やしめ飾り、鏡餅などです。
これらの正月飾りは正月に各家にやってくる歳神(年神)様をお迎えする風習が現在も形として残っているものです。
門松の飾る時期と意味とは
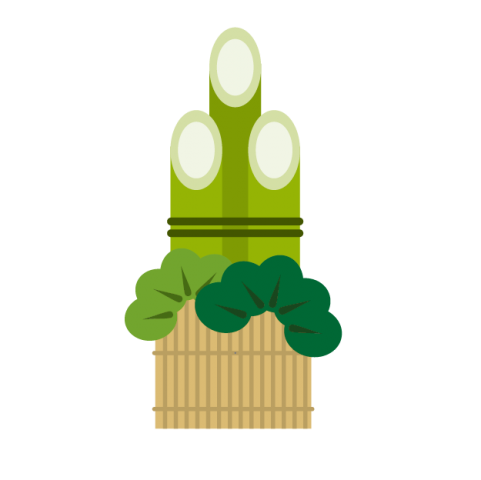
門松はお正月に歳神様をお迎えするために飾るものです。
松の内(12月13日以降)ならいつでも飾ってもよいですが、お正月の直前で「二重苦」を連想させる29日、神をおろそかにする「一夜飾り」となってしまう30日(晦日)、31日(大晦日)を避けた28日に飾るのが一般的となっています。
門松を片付ける時期も松の内までなので、一般的には1月7日までで、地域によって1月15日や1月20日までのところもあります。
しめ飾りの飾る時期と意味とは
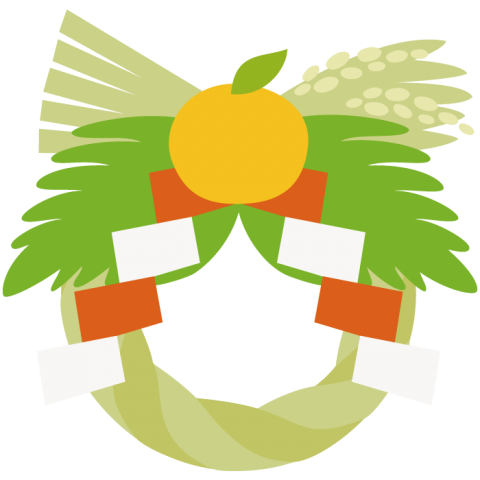
しめ飾りとはしめ縄に橙や譲り葉などの縁起物を飾りつけたものです。
神社やご神木などにしめ縄をするのと同じように、歳神様を迎え入れる自宅が神聖で清らかな場所であることを示すために飾るようになったと言われています。
しめ飾りも地域によって様々なタイプがあります。
しめ飾りも門松と同じく松の内以降で12月28日に飾り、1月7日や15日に外します。
外したしめ飾りは15日のどんど焼き(左義長)で焼きます。
鏡餅の意味と飾る時期、鏡開き
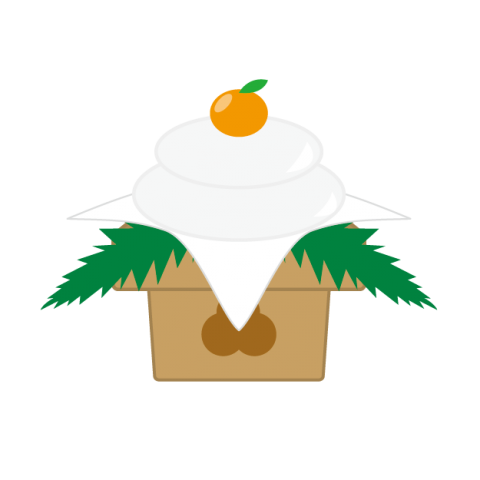
鏡餅は歳神様へのお供え物として飾られます。
飾る場所は床の間や神棚、それらがない場合は家の最も奥まった場所に置くようにします。
一般的には大小二つの丸餅と橙を飾りますが、串柿や干しするめなどを飾る、橙の代わりに温州みかんを使うなど、地域によっても様々です。
飾り始める時期も他の正月飾りと同様に12月28日に飾ることが多いですが、正月が終わるとお供えしていた鏡餅をおしるこやお雑煮などにして食べる鏡開きが行われます。
鏡開きの時期は松の内が終わった後の1月11日に行われます。
喪中のお正月は正月飾りを行わないほうがよい
正月飾りは歳神様を迎え入れ、旧年を無事に過ごせたことを感謝し、新年をお祝いするためのものです。
しかし、喪中なのでお祝い事は自粛する必要があり、旧年中に不幸があったので、やはり喪中に正月飾りを行うことは適切ではありません。
喪中の神棚のお札やしめ縄の取り替え
なお、正月飾りの際に、神棚がある家では神棚を掃除し、お札やしめ縄を新しくする必要があります。
神棚は神道ですので、神道における忌中50日間の間は封印されます。
この忌中に正月を迎えた場合は、お札やしめ縄の交換はできません。
忌明け後であれば、喪中であってもお札やしめ縄の交換は可能です。ただし、喪中なので神棚には正月飾りなどは行わず、普段通りにしておきます。
喪中の正月飾りのまとめ
- 正月飾りは新年のお祝いの意味も含めているので、喪中の場合は控える
- 神棚は喪中であっても忌明け後であれば、新年の清掃を行ってもよい。ただし、神棚への正月飾りは行わない
参考 喪中はがき印刷挨拶状ドットコム