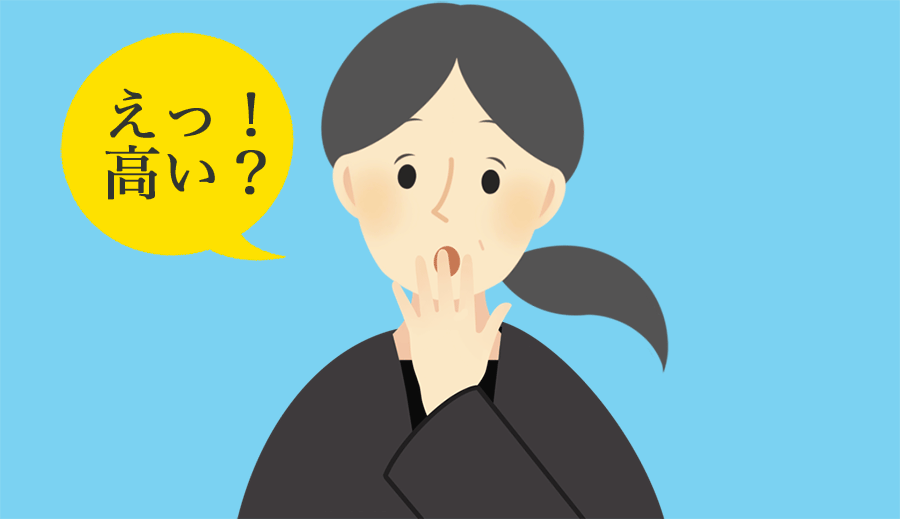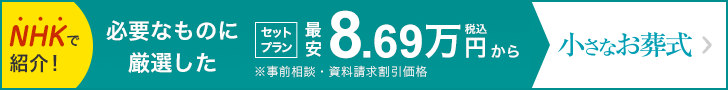葬儀で不安に感じることのダントツは、葬儀の費用に関することだと言われています。
そこでこの記事では、「葬儀費用には、一体いくらかかるのか?」「お布施はいくら包めばいいのか?」といった、葬儀にかかるお金について徹底的に解説していきます。
(この記事の下に移動します。)
お葬式にかかる費用の内訳
お葬式の費用は、
- 葬儀そのものにかかる費用
- 飲食接待費
- 寺院費用
大きくこの3つに分類されます。
それぞれの内訳は以下の通りです。
1、葬儀そのものに係る費用について
文字通り、通夜や葬儀そのものにかかる費用です。
斎場使用料をはじめ、祭壇や棺、火葬場や霊柩車など、葬儀社に支払う費用全般がそれにあたります。
一般的に葬儀社の提示する基本プランに加えて、様々なオプションなどが加えた金額になります。
2、飲食接待費について
通夜振る舞いや精進落としなどの会食にかかる費用です。あるいは、会葬返礼品や香典返しなどの返礼費用などを指しています。
金額は会葬者の数によって左右されます。
3、寺院費用について
僧侶に渡すお布施や戒名料、他にもお車代や御膳料など、寺院に支払う費用です。
金額を訪ねても「お気持ちで」と言われる事が多く、明確な金額が明示されないので喪主が最も頭を悩ませる項目でもあります。
葬儀費用の全国データ
では、葬儀費用の全国平均はどの程度なのでしょうか?
お葬式費用の全国平均は?
日本消費者協会の「第10回葬儀に関するアンケート調査」によると葬儀費用の全国平均額(寺院費用などすべて含む)は約189万円でした。
| 葬儀費用の合計 | 約189万円 |
|---|---|
| 葬儀そのものにかかる費用 | 約122万円 |
| 飲食接待費 | 約34万円 |
| 寺院費用 | 約45万円 |
ただし、あくまでも平均値です。また、このアンケート自体のサンプリング手法の粗さが指摘されていますので参考程度とお考えください。
気になるのは「心づけやお布施の額」
同アンケートでは「家族の葬儀を経験して困ったこと」の第一位が「心づけやお布施の額」(37%)となっています。
やはり、葬儀費用の中でも最もわかりにくい費用で多くの人が不安に感じている部分と言えそうですね。
寺院費用の中身
地域や宗派や寺ごとによって異なる価格なのであくまで参考程度となりますが、
本来「寺院費用」は寺に対する寄付という形なので、「読経料」や「戒名料」といったサービスに対する対価に相当するものとなります。
読経料
一般的に通夜から初七日法要までの読経をお願いすると、20~25万円程度を包むことが多いと言われています。
戒名料
「◯◯院◯◯居士」のように「◯◯院」の院号の部分と「居士」の位号を含めて戒名と呼びます。
戒名のランクによってお布施に包む金額も増えていきます。
位号はまず「信士・信女」があります。
その上に「居士・大姉」というランクがあり、これに院号がつくかつかないかでさらに値段が上下します。
信士・信女は檀家であれば無料であることも。
以下は参考程度の相場です。
| 戒名 | 参考相場 |
|---|---|
| 信士・信女 | 20~30万円 |
| 居士・大姉 | 30~50万円 |
| 院信士・院信女 | 50~100万円 |
| 院居士・院大姉 | 100万円~ |
実際は宗派やお寺や地域などにより差がありますので、檀家総代に尋ねてみるか、住職が教えてくれる場合もあるでしょう。
また、戒名を付けずに俗名(生前の名前)のままを希望する人もいます。しかし、戒名なしの場合そのお寺の墓地への納骨を断られる事がありますのでご注意ください。
その他の費用
お車代
僧侶が式場まで自分の足で来た場合に、交通費として包むものです。相場は5000円〜1万円程度。
タクシーを利用した場合は直接タクシー代を支払う場合もあります。
御膳料
通夜振る舞いや精進落としなどの会食に僧侶が参加しない場合に食事代として渡すものです。
相場は5000円~1万円程度です。慌てないために事前に会食に参加するかどうかを僧侶に確認しておきましょう。
イオンが自社サービスで打ち出したお布施の価格目安
平成22年に葬儀紹介サービスを手がけるイオンが「布施の価格目安」を打ち出したところ、一部の仏教団体に「お布施に定価はない」という報道がありました。
その後、反発を受けてイオンはWebサイトから価格目安を削除しましたが、以下のような目安を出していました。
| 内容 | お布施の目安 |
|---|---|
| 読経一式+信士信女戒名 | 25万円 |
| 読経一式+居士大姉戒名 | 40万円 |
| 読経一式+院号居士大姉 | 55万円 |
| 炉前読経+信士信女戒名 | 10万円 |
あくまでもお布施の目安です。
各社の定額お布施・僧侶派遣・寺院紹介サービス
さて、最近ではインターネットの葬儀紹介会社などが「僧侶派遣」や「寺院紹介のサービス」を行っています。
付き合いのある寺がない人に向けてのサービスです。
価格はこちらをご覧ください。
| 直葬 | 一日葬 | 一般葬 | |
|---|---|---|---|
| イオンのお葬式 | 45,000円 | 75,000円 | 150,000円 |
| 小さなお葬式 | 60,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
| お坊さん便 | 55,000円 | 85,000円 | 160,000円 |
これらの大きな特徴は、読経一式と普通戒名(信士・信女など)の授与も含めていることです。
そのため、基本的には追加料金なしで明示されている価格で僧侶が派遣されるということになります。
ただし注意点としては、菩提寺(付き合いのあるお寺)がある場合は事前に許可を得ておかないとトラブルの元となるのでご注意ください。
葬式費用の注意点
葬式費用の注意点をみていきます。
葬儀社の基本プランを確認しよう
お葬式にかかる費用で「葬儀そのものにかかる費用」がありますが、これらの中身は多岐にわたります。
- 斎場使用料
- 火葬代
- 休憩室代
- 霊柩車
- ドライアイス代
- 司会代
- 祭壇
また、棺や焼香などに至るまで、葬儀には様々なものが必要だからです。
葬儀社は基本的にはこれらを含んだサービスプランを複数用意しており、遺族がそのプランを選び、細かい部分を決めていくというのが基本になります。
プランに含まれていないものには追加料金がかかります
「◯◯万円のプランを申し込んだのに、実際は追加費用がたくさんかかって最終的には◯◯万円になった!」
という追加料金の話はお葬式ではよく耳にする話です。
例えば葬儀までに遺体を保存しておくためのドライアイスは1日あたり10kgは必要ですが、葬儀までの日程があいた場合はその日数分のドライアイス代が必要になってきます。
また、祭壇や棺を豪華にしたりというオプション価格や、火葬代などは含まれていなかったりなどと、思いもよらないところで追加費用がかかることがあります。
重要なことはプランに含まれているものと含まれていないものを把握することです。
逆に言うと、これらを明示している葬儀社は優良な葬儀社と言えるでしょう。
会葬者の人数を把握する
葬儀の費用を決定付ける大きな要素が会葬者の人数です。
飲食接待費の金額に直接影響するほか、香典による収入金額にも影響するので葬儀費用を考える上で重要な要素と言えます。(香典の詳細は香典のページをご参照ください)
葬儀社と葬儀の打ち合わせをする際に必ず聞かれるものですが、性格な人数ではなく大雑把な人数で大丈夫です。
- 親戚関係
- 故人の交友関係
- 故人の会社の繋がり
などから人数の予測を立てます。
逆に言うと、家族葬などの場合は予め会葬者を抑えるように、訃報を後から出すなど工夫する必要があります。
葬儀後のことも頭に入れておく
葬儀にかかる費用と葬儀後にかかる費用は切り離すことができません。
葬儀が終われば、
- 四十九日や一周忌などの定期的な法要
- お墓、仏壇、位牌などの用意
また、お寺の墓地に納骨を考えている場合は戒名などが必要な場合もあります。
基本的には菩提寺と相談して進めることになるので、葬儀後のことも頭に入れておくとよいでしょう
葬儀費用を抑えるための工夫
葬儀費用を安く抑えるためには次をご検討ください。
市民葬・区民葬・規格葬儀を利用する
一部地域では自治体と葬儀社が協力して、比較的安価な市民葬・区民葬・規格葬儀と呼ばれるサービスを受けられることがあります。
一般的な葬儀を安く行えるように工夫されています。しかし、自治体によっては扱っていないものもあるので確認してみましょう。
また、この場合も追加料金などが発生する場合もあるので注意が必要です。
市民葬・区民葬・規格葬儀について詳しく知りたい方は下記のページをお読みください。
 本当に安くなる?自治体も関わる「市民葬・区民葬・規格葬儀」
本当に安くなる?自治体も関わる「市民葬・区民葬・規格葬儀」
互助会に入る
互助会は「葬儀の保険」のようなものです。
掛け金を積み立てることで積立金以上の役務(サービス)を受けることができます。
満額に達していない場合でも、葬儀の段階で差額を納めればサービスを受けられることが多く、葬儀場所が遠方の場合でも提携している互助会への移籍も行えることが多いです。
一方で、退会のトラブルが多かったり、互助会が経営破綻するリスクもあるなど注意点も。
互助会について詳しく知りたい方は下記のページをお読みください。
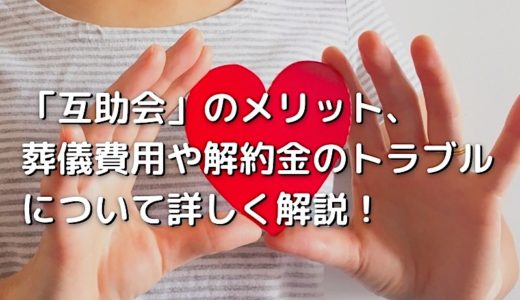 「互助会」のメリットと、葬儀費用や解約金のトラブル
「互助会」のメリットと、葬儀費用や解約金のトラブル
家族葬・直葬・一日葬などを利用する
最近は小規模で質素な葬儀が人気があり、家族や親しい人だけなどに絞った家族葬や、火葬のみの直葬、通夜を省略した一日葬などが人気があります。
質素で親しい人のみという最近の需要を取り入れていますが、親戚とのトラブルなどになったり、菩提寺の理解を得る必要があるなど注意が必要です。
また、会葬者を限定することで小規模な葬儀にすることができますが、その分香典も減ることになるので、やり方を間違えれば結果的に葬儀費用がかかることもあります。
家族葬、直葬、一日葬について詳しく知りたい方は下記のページをお読みください。
 家族葬のメリット、費用を抑えるコツ。相場は?香典と辞退についてまで
家族葬のメリット、費用を抑えるコツ。相場は?香典と辞退についてまで
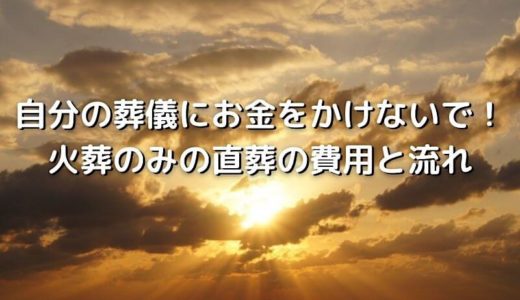 自分の葬儀にお金をかけないで!火葬のみの直葬(火葬式)の費用と流れ
自分の葬儀にお金をかけないで!火葬のみの直葬(火葬式)の費用と流れ
 小規模でもしっかり送りたい 一日葬
小規模でもしっかり送りたい 一日葬
公的扶助制度を利用する
葬儀費用を抑える工夫ではないですが、身内が亡くなって葬儀を行うともらえるお金があります。
国民健康保険や会社の健康保険の加入者は「葬祭費・埋葬料」をもらうことができます。
また、国民年金や厚生年金の加入者は「遺族基礎年金・遺族厚生年金」をもらえる場合もあります。
死亡に関する公的な給付制度を確認しておきましょう。
 「死亡後・葬儀後にする手続き」まとめ。やることは山積み!
「死亡後・葬儀後にする手続き」まとめ。やることは山積み!
 もらえる年金をもらっていますか?「遺族年金の手続き」まとめ
もらえる年金をもらっていますか?「遺族年金の手続き」まとめ
定額葬儀サービスを利用する
最近では民間の葬儀サービスでも、低価格かつ明朗会計をうたう葬儀社が出てきています。
例えば、全国展開する「小さなお葬式」では、セットプランで格安のお葬式をうたっており、仮に不当な請求があった場合には返金保証もつけています。
参考 公式サイト小さなお葬式同様のサービスを行っている会社は「イオンのお葬式」と「よりそうお葬式」があります。
これらのサービスを徹底比較した記事がありますので、ご興味ある方はそちらもお読みください。
 どっちがいいの?「小さなお葬式」と「イオンのお葬式」徹底比較!
どっちがいいの?「小さなお葬式」と「イオンのお葬式」徹底比較!
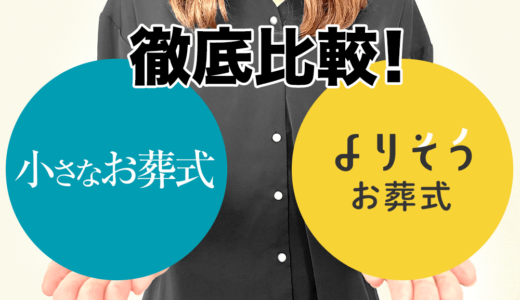 格安プラン葬儀「小さなお葬式」と「よりそうお葬式」費用などを徹底比較
格安プラン葬儀「小さなお葬式」と「よりそうお葬式」費用などを徹底比較
まとめ
いかがでしたか?
ここまで葬儀費用を安く抑えるためにできる工夫をお話していきました。
この記事でお葬式にかかる費用をさげるお手伝いができましたら幸いです。